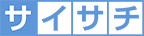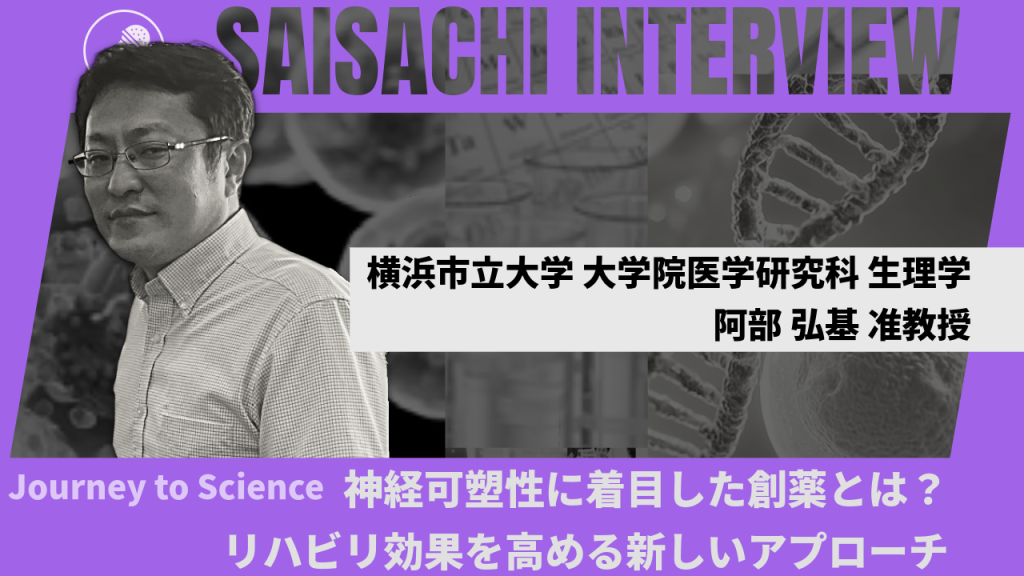
今回のインタビューでは横浜市立大学医学部生理学 准教授 阿部 弘基先生にお話しをお伺いしました。神経可塑性の研究の最前線をお伝えします。
目次
- インタビュー
- 神経可塑性との出会いとリハビリテーションへの着目
- 基礎と臨床をつなぐ研究の面白さと今後の挑戦
- 研究を支える「欠かせないもの」
- 先生プロフィール情報
- 専門用語解説
- まとめ
インタビュー 「神経可塑性に着目した創薬とは?リハビリ効果を高める新しいアプローチ」
神経可塑性との出会いとリハビリテーションへの着目
―― 本日はありがとうございます。早速ですが、先生が現在の研究の道に進まれた「きっかけ」についてお聞かせいただけますでしょうか。――
もともと科学研究に携わりたいと思ったきっかけは、中学生の頃です 。物理や数学がすごく面白いと感じ、科学の世界そのものに憧れがありました。当時は講談社のブルーバックスや科学雑誌の『Newton』を毎月読むような中学生だったので、将来は必ず理系の研究に進もうと考えていましたね 。
その後、紆余曲折あり、最初は医学部とは違う大学に進学しました。しかし、様々なことを学び、多くの人と出会う中で、やはり「科学を人の役に立てたい」という思いに至り、5年遅れで医学部に入り直したんです 。医学部に入った当初から、大学に残って研究を続けたいという気持ちがありました 。
―― 医学部の中でも、特に脳神経内科学の道を選ばれたのはなぜでしょうか。――
医学部入学当初は精神医学に非常に興味があったのですが、内科学を真面目に勉強するうちに、その論理的な考え方の面白さに惹かれるようになりました 。そこで、精神医学と内科学、両方の要素を持つ「脳神経内科学」という領域に興味が移っていきました 。脳神経内科学は、いわゆる難病が多く、まだ治らない病気がたくさんある領域です 。だからこそ研究のしがいがあると感じましたし、脳の神経回路という実態に即した研究ができるのではないかと考えました 。
学生時代に「脳神経内科の領域で何か良い研究をしたい」と考えていた時、現在のメンターである高橋琢哉のものの面白さと、この概念を基にした診断法や治療法がまだ確立されておらず、やるべきことが沢山ある点に魅力を感じました 。
そこから、脳神経内科学と神経可塑性をどう結びつけるかを考え、「リハビリテーション」というテーマにたどり着いたのです 。脳神経内科の代表的な疾患である脳卒中では、脳の損傷によって手が動かなくなっても、リハビリによってある程度回復します 。これは、残された脳が神経可塑性を発揮して、失われた機能を補おうと回路を書き換えるからです 。この「脳の書き換え」を促進するような薬を見つけ、リハビリの効果やスピードを高めることを目指す、というのが現在の研究の出発点です 。
「回復」を目指す創薬:疾患修飾薬との違い
―― 薬というと症状を抑えるイメージが強いですが、先生の研究は「回復を促す」という新しいアプローチなのですね。――
はい、私たちが目指しているのは「リカバリー(回復)」を促す薬です。最近、「疾患修飾薬」という言葉があると思います。例えばアルツハイマー病の新しい薬は、脳から原因物質(アミロイドβ)を取り除くことで病気の進行のスピードを抑えるものですが、悪くなってしまった認知機能を回復させるものではありません。原因物質を減らしてはいますが、「元に戻している」わけではないのです。
一方で、リハビリテーションというのは、言葉の語源の通り、元の機能にたどり着けるようにするということです。患者さんからしてみれば、脳卒中で動かなくなった手が自分の意思で再び動くようになる、というのが分かりやすい願いですよね。私たちは、この「元に戻る」という部分を、可塑性の仕組みに基づいた創薬でどう加速できるか、という点を追求しています。これは、病態の原因に基づいた治療や創薬とは、少し違うところにあるアプローチだと考えています。
研究の挑戦、そして欠かせないもの
――研究を進める上での難しさや、今後の挑戦について教えてください。――
難しさを感じるのは、基礎研究で分かったことを臨床で証明するために、大規模な臨床研究が必要になる点です。多くの病院や部署との連携、倫理的な規則の遵守など、基礎研究のように自分の裁量で自由に計画を組むのとは違い、多くの制約の中で進める必要があります。
今後の挑戦としては、パーキンソン病やアルツハイマー病のように「ゆっくりと」機能が失われていく慢性的な疾患に取り組みたいです。そうした病気の進行過程で、脳が失われゆく機能にどう抗い、代わりの神経回路をどう作っているのか、その「機能代償」のメカニズムを解明し、それに基づいた効果的なリハビリテーションプログラムを構築していきたいです。
――最後に、先生の研究に欠かせない機械やツールについて教えていただけますか。――
今は人の脳画像研究が中心なので、PET(陽電子放出断層撮影)装置は欠かせません。博士課程の頃に長年愛用していたのは、脳に凍結損傷を作るための「クライオプローブ」という器具です。これはもともと網膜剥離の手術に使うもので、先端をマイナス80度くらいに急速冷却できるんです。これを脳の表面に当てることで、脳卒中のモデルを安定して作ることができ、私の研究のベースとなる非常に重要な機械でした。
―― 本日は貴重なお話をありがとうございました。――
先生プロフィール情報

今回のインタビューでは神奈川県金沢区にある横浜市立大学の福浦キャンパスにお伺いさせていただきました。研究室からも海が臨める素敵なロケーションのキャンパスでした。
阿部 弘基 准教授
公立大学法人 横浜市立大学大学院医学研究科 生理学 准教授
研究分野:ライフサイエンス、神経内科学
発表論文情報:
1. Edonerpic maleate enhances functional recovery from spinal cord injury with cortical reorganization in non-human primates. Koichi Uramaru, Hiroki Abe, Waki Nakajima et al., Brain Communications, 2025
2. CRMP2-binding compound, edonerpic maleate, accelerates motor function recovery from brain damage. Hiroki Abe et al., Science 2018
3. Systemic increase of AMPA receptors associated with cognitive impairment of Long COVID. Yu Fujimoto, Hiroki Abe et al., Brain Communications, 2025
4. Differentiation between bipolar disorder and major depressive disorder based on AMPA receptor distribution. Sakiko Tsugawa, Yuichi Kimura, Junichi Chikazoe, Hiroki Abe et al., Frontiers in Neural Circuits, 2025
引用:researchmap(https://researchmap.jp/05150606/)
専門用語解説
神経可塑性(しんけいかそせい) / Neuroplasticity
脳が経験や学習、あるいは脳損傷などに応じて、神経回路のつなぎかえなどを通じて、その構造や機能を変化させる能力のこと。リハビリテーションによる機能回復の基盤となる重要なメカニズムです。
機能回復 (きのうかいふく)/ Functional Recovery
脳卒中などの疾患によって失われた運動機能や感覚機能などが、リハビリテーションや治療によって取り戻されること。阿部先生の研究は、この機能回復を薬剤によって促進することを目指しています。
リハビリテーション / Rehabilitation
疾患や外傷によって生じた機能障害を回復させ、社会生活への復帰を目指す医療アプローチ全般を指します。運動療法だけでなく、認知行動療法や作業療法など、多様な手法が含まれます。
創薬(そうやく)/ Drug Discovery
新しい医薬品を開発する研究プロセスのこと。病気のメカニズム解明から、候補となる化合物の探索、有効性や安全性の検証まで、非常に長い期間と多大なコストを要する挑戦的な研究分野です。
疾患修飾薬(しっかんしゅうしょくやく)/ Disease-Modifying Drug
対症療法薬とは異なり、病気の根本的な原因に作用し、その進行を抑制または遅延させる薬剤。インタビュー中では、アルツハイマー病治療薬を例に、機能回復を目指す薬剤との違いが述べられています。
脳画像研究 (のうがぞうけんきゅう)/ Brain Imaging Research
fMRIやPETなどの非侵襲的な技術を用いて、生きている人間の脳の構造や活動を視覚化する研究手法。神経可塑性によって脳がどのように変化しているのかを客観的に評価するために用いられます。
まとめ

今回は、「神経可塑性に着目した創薬」という、未来につながる大変興味深いお話をありがとうございました。
先生の中学生の頃からの科学への純粋な憧れ、そして「科学を人の役に立てたい」という強い思いが現在の「回復を促す」という新しいアプローチにつながっていることが大変理解できました。
特に、脳卒中後のリハビリテーション効果を薬で高めるという研究は、多くの患者さんにとって希望となるものと思います。疾患修飾薬との違いを明確にし、リハビリテーションの語源の通り「元に戻る」ことを追求する先生の姿勢に感銘を受けました。
今後は、パーキンソン病やアルツハイマー病といった慢性疾患における機能代償のメカニズム解明と、それに基づくリハビリテーションプログラムの構築という今後のご活躍を期待しております。
本日は貴重なお話をありがとうございました。
(インタビュー担当:榊原(理科研神奈川支店))