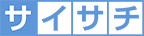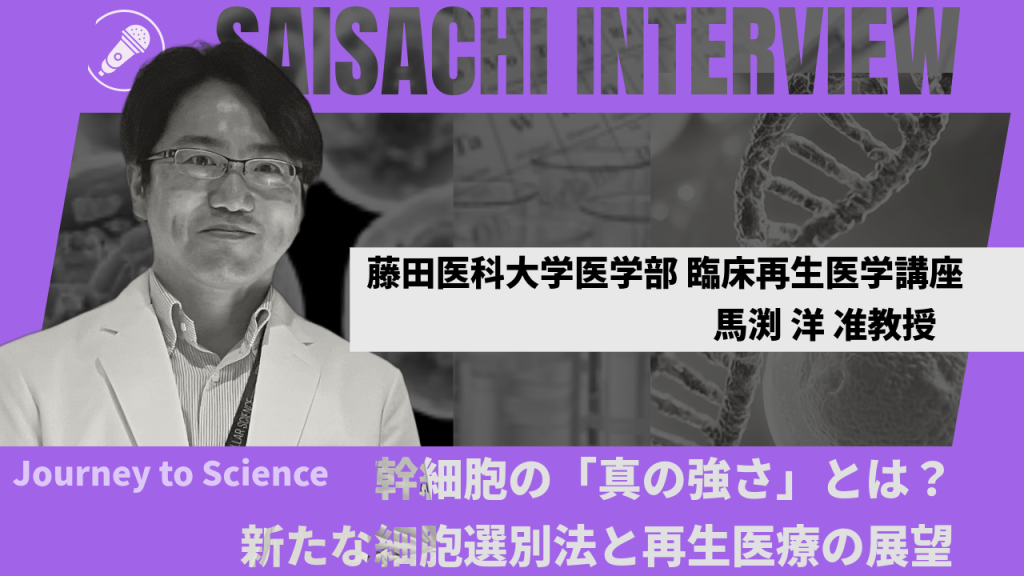
今回サイサチでは藤田医科大学東京 先端医療研究センター 馬渕 洋 准教授にお話を伺わせていただきました。本インタビューでは、再生医療の展望について、先生の研究をお伝えいたします。
目次
- インタビュー
- 研究に進んだきっかけは?幹細胞研究の魅力と未来を切り拓く新たな視点とは?
- ポイントは「ストレス!?」現在の挑戦
- オープンラボでのイノベーション!ラボ環境の魅力
- 研究に欠かせないソリューションとは?
- 先生プロフィール情報
- 専門用語
- まとめ
インタビュー「幹細胞の「真の強さ」とは?新たな細胞選別法と再生医療の展望」
研究に進んだきっかけは?幹細胞研究の魅力と未来を切り拓く新たな視点とは?
―― 本日はお忙しい中、ありがとうございます。早速ですが、先生が研究の道に進まれたきっかけについてお聞かせいただけますでしょうか。――
きっかけは2つありまして、しっかりしたバージョンと、少し冗談のようなバージョンがあります。
――ぜひ両方お聞かせください。――
冗談のようなバージョンが、実は真実に近いかもしれません。子供の頃に読んでいた漫画『ドラゴンボール』で、ピッコロの腕がなくなってもまた生えてくるのを見て、「なんで人間にはあの能力がないんだろう」と素直に思ったのが最初のきっかけです。
ちょうど私が学部生で、大学院に進むか就職するかを考えていた時期に、トカゲの尻尾が再生する仕組みを人に応用しようとする「再生医療研究」に出会いました。 プラナリアやトカゲには再生能力があるのに、なぜ人にはないのか。人も本来は腕を生やすような再生能力を持っているのではないか、という話に非常に興味を惹かれました。発生学や幹細胞研究という分野にグッと引き込まれた瞬間でしたね。
――それが、先生の研究の原点なのですね。もう一つの「しっかりしたバージョン」についても教えてください。――
はい。それは卒業研究で配属された研究室で「人工皮膚」の技術に触れたことが大きいですね。フラスコの中で培養した人間の皮膚細胞が、ほんのわずかな量からプール一面ほどの広さにまで増える事を知り、驚きと共に「これは絶対に治療に使える」と感じました。 当時は、がん細胞を培養して薬を見つけるプロジェクトが盛んに行われていた時代背景もあり、「自分は医者ではないけれど、この技術で人を助けられるかもしれない」と、再生医療の可能性に強く魅力を感じました。
実際に、重度の火傷や床ずれで苦しむ患者さんに、培養細胞を組み込んだ人工皮膚を貼り付けると、みるみるうちに治っていく臨床研究を目の当たりにしました。 私が研究を始めた頃は、日本再生医療学会が立ち上がった時期で、ちょうど日本で再生医療が盛り上がっているタイミングでした。そんな中、体の中にある再生の源である「間葉系幹細胞」の研究をしようと決意し、以来ずっと同じ細胞をテーマに研究を続けています。
――当時から一貫して幹細胞研究に携わってこられたのですね。特に印象に残っている発見や考え方はありますか?――
初期に取り組んだ人工皮膚の研究では、「なぜ他人の細胞を移植すると傷が治るのか?」という疑問がありました。 その結果明らかとなったのは、移植した細胞そのものが組織を形成して再生を担うのではなく、細胞から放出されるタンパク質、いわゆるサイトカインが組織の細胞を刺激し、修復を促していたという点です。
「それならタンパク質のみを投与すればよいのではないか?」と考えるかもしれません。しかし、細胞治療の本質は「細胞が必要な時に、必要な種類・量のタンパク質を継続的に分泌する」という点にあります。この概念を知ったとき、私は幹細胞が有する高度な適応能力―すなわち「状況に応じて応答し続ける能力」こそが、従来の薬剤では到達できなかった治療効果をもたらすと確信しました。この概念は非常に魅力的であり、私が幹細胞研究に引き込まれていく大きなきっかけとなりました。
――非常に面白いお話です。先生は現在、再生医療学会の理事も務められていますが、どのような活動に力を入れていますか?――
特に「若手の育成」には力を注いでいきたいと考えています。山中先生のiPS細胞技術によるノーベル賞受賞以降、研究分野は大きな注目を集めてきましたが、実際には研究者を志す若手が減少している印象があります。次世代を担う研究者を育成し、彼らが活躍できる場を整えることこそが、現在の私に課せられた使命だと考えています。私自身も学生時代、幹細胞若手会(通称つくしの会)を通じてネットワークを広げた経験があり、その経験を活かし、若手が積極的に学会に参加できる仕組みづくりを進めていきたいと思います。
ポイントは「ストレス!?」現在の挑戦
――現在の研究テーマについてお伺いします。先生のテーマの面白いところや、今まさに挑戦されていることについて教えてください。――
今ちょうど、新しいテーマに取り組んでいるところです。これまで私は、体内に存在する能力の高い幹細胞を、フローサイトメーターという機械を使って分離する技術を開発してきました。 しかし機械が無いと分離できないし、分離するのにはある程度コストがかかってしまいます。最近、全く違うアプローチでそれらの問題をクリアし、幹細胞を分離する方法を発見しました。それは、幹細胞の「環境に適応する能力」を利用する方法です。
―― 環境に適応する能力、ですか。――
はい。例えば、細胞の培養環境から栄養を極端に減らすといった飢餓ストレスを与えると、ほとんどの細胞は死んでしまいます。しかし、その過酷な環境でも生き残る幹細胞がいて、調べてみると非常に能力が高いことが分かりました。 私はこれを、冗談めかして「パワハラ耐性株」と呼んでいます。
これはダーウィンの進化論で、最も「強い種」が生き残るのではなく「環境に適応した種」が生き残る、という考え方に通じます。 栄養だけでなく、pH(酸性・アルカリ性)や酸素濃度、物理的な刺激(メカニカルストレス)など、様々な環境に適応をできる細胞を集める事で、機械を使わずに良い細胞だけを選別できるのではないかと考えています。 この環境適応による選別法が確立できれば、再生医療のコストを下げ、より多くの患者さんに治療を届ける技術になるかもしれないと期待しています。
―― 「パワハラ耐性株」、非常にユニークで興味深いネーミングですね。その幹細胞には何か特徴があるのでしょうか?――
非常に良い質問ですね。そこがまさに研究の核心で、飢餓ストレスに耐えられる細胞は「代謝」の仕組みが違うことが分かってきています。 環境の変化に応じて、エネルギーの使い方を柔軟に切り替えられる細胞が生き残るのです。今はその詳細なメカニズムを解明し、論文にまとめているところです。
オープンラボでのイノベーション!ラボ環境の魅力
―― 先生が現在所属されている研究施設は、企業との連携も活発なオープンな環境だとお伺いしました。その魅力についてもお聞かせください。――
はい、私がいる羽田のラボはオープンラボで、製薬企業の方など、アカデミア以外の研究者と日常的に一緒に研究を進めています。 自由な発想で真理を探究するアカデミアと、製品化やビジネスモデルを重視する企業とでは、研究に対する視点や戦略が全く異なります。 この違いを肌で感じながら研究できるのは非常に刺激的ですし、将来、自分の研究成果を社会実装する上でも貴重な経験になっていると感じます。
また、この羽田の拠点は、日本の再生医療研究開発の重要拠点と位置づけられており、多くの企業や研究者が集結しています。 「日本の再生医療の未来背負う!」くらいの覚悟を持って、皆で一丸となって取り組んでいます。
―― 研究一筋という印象の先生ですが、研究以外に熱中されていることはありますか?――
最近はラグビーに夢中ですね。 実は私自身ではなく、中学生の息子がラグビーを始めまして。 私も妻も全くの素人だったのですが、息子がどんどんのめり込んで、我が家は今ではラグビー一色になっています。 ラグビーの試合を見たり息子から戦略の説明を聞いたりするのが休日の楽しみです。
ラグビーは見ていてハラハラするほど激しいスポーツで、怪我など心配しています。ただ、この厳しい環境に適応し乗り越える経験が、息子を強くしてくれると信じて、サポートは惜しまないようにしています(笑)。
研究に欠かせないソリューションとは?
―― 最後に、先生の研究に欠かせない機器や試薬があれば教えてください。――
それは間違いなく「フローサイトメーター」ですね。 私の研究者人生は、この機器に育ててもらったと言っても過言ではありません。細胞を一つひとつ分離・解析するこの技術を突き詰めたおかげで、「細胞分離のことなら馬渕に」と認知していただき、多くの共同研究や研究者ネットワークの形成につながりました。
特定のメーカーにこだわるのではなく、全てのメーカーの機種を扱えるように心がけています。 これからも、このフローサイトメトリー技術を大切にしながら、新たな研究に挑戦していきたいですね。
――先生ご自身のキャリアから現在進行形の刺激的な研究、そしてプライベートな一面まで、本日は大変興味深いお話をありがとうございました。――
先生プロフィール情報

今回のインタビューは、東京・羽田エリアにある「藤田医科大学東京 先端医療研究センター内の「再生・細胞医療開発講座」で行わせていただきました。
馬渕 洋 准教授
藤田医科大学医学部 臨床再生医学 准教授
藤田医科大学東京 先端医療研究センター
藤田医科大学 医学部 再生・細胞医療開発講座
専門分野
幹細胞生物学
所属学会
日本再生医療学会、ダイバーシティー委員会委員、日本再生医療学会、再生医療推進戦略委員、日本再生医療学会、国際委員会委員、日本再生医療学会、U-45選抜メンバー、国際幹細胞学会(ISSCR)、Nest generation of leaders メンバー、日本サイトメトリー学会 代議員
専門用語解説
幹細胞 (かんさいぼう) /Stem cell
自分自身を複製する能力(自己複製能)と、体を構成する様々な種類の細胞に変化する能力(分化能)を持つ特殊な細胞のこと。再生医療において、失われた組織や機能を修復するための源として期待されています。
再生医療 (さいせいいりょう) / Regenerative medicine
病気や怪我によって失われた体の組織や臓器の機能を、幹細胞などを用いて回復させることを目指す医療分野。本記事では、培養した皮膚の移植などが例として挙げられています。
フローサイトメーター / Flow cytometer
レーザー光を用いて、液体中を流れる細胞や粒子を一つひとつ高速で分析・分離(ソーティング)する装置。特定の性質を持つ細胞だけを選び出す研究に不可欠な機器です。馬渕先生の研究者人生において重要な役割を果たしたと述べられています。
サイトカイン / Cytokine
細胞から放出されるタンパク質の一種で、細胞間の情報伝達を担います。免疫応答の調節や細胞の増殖・分化など、多様な生命現象に関わっています。記事中では、移植された細胞が放出するサイトカインが組織の修復を促す、という発見が語られています。
代謝 (たいしゃ) / Metabolism
生物が生命を維持するために体内で起こす化学反応全般のこと。栄養素からエネルギーを取り出したり、体に必要な物質を合成したりする働きを指します。ストレス環境下で生き残る細胞は、この代謝の仕組みを柔軟に切り替える能力が高いと考察されています。
iPS細胞(あいぴーえすさいぼう)(人工多能性幹細胞) / iPS cell (induced pluripotent stem cell)
皮膚などの体の細胞に特定の遺伝子を導入することで作製される、幹細胞の一種。様々な種類の細胞に分化する能力を持ち、再生医療研究の中核を担う技術の一つです。
まとめ

本インタビューでは、馬渕先生の「再生療法への思い」や「幹細胞研究の可能性」など非常に興味深いお話を聞くことができ、現場担当者として大変貴重な機会となりました。
特に幹細胞の分離方法において、今までとは別のアプローチ「環境に適応する能力」を利用する方法には驚きました。
この新たな方法が確立された時、再生医療の発展に貢献できる可能性を感じました。
今後、馬渕先生の研究内容に沿った製品やサービスを提案・提供していき、研究成果のお役に立てるように努めてまいります。
(インタビュー担当:佐藤(理科研鶴見営業所))