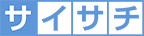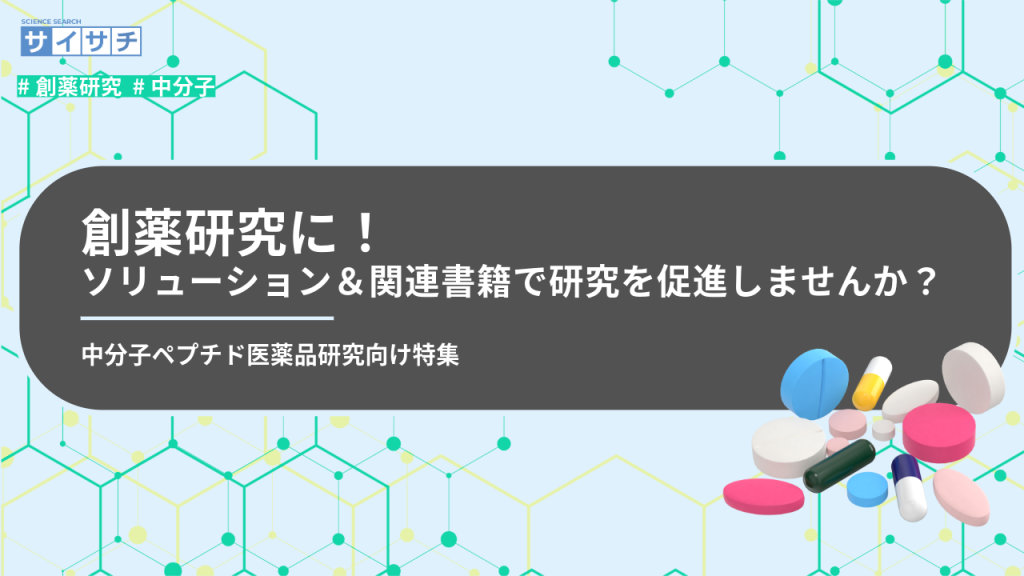
近年、創薬研究において中分子ペプチド医薬品が注目を集めています。従来の低分子医薬品や抗体医薬品が持つ懸念点を克服する可能性をもつ新しいモダリティとして、各処で活発な研究開発が進められています。
今回サイサチの本ページでは、中分子ペプチド医薬品の研究開発に必要不可欠なソリューションと、理解を深めるための書籍をご紹介致します。
目次
中分子医薬品とは?
中分子医薬品とは、低分子(分子量約500以下の化学合成で得られる化学物質)と高分子(分子量数千以上の抗体医薬品などのバイオ医薬品)の間に位置する、分子量500~2000程度の医薬品を指します。主にペプチドや核酸を用いて作られ、低分子医薬品と、高分子医薬品の両者の利点を併せ持つことが期待されています。
中分子ペプチド医薬品の研究開発プロセスは多岐にわたります。
- ペプチド・核酸の合成と精製
- 合成された分子の構造解析と品質評価
- 標的分子との相互作用解析
- 薬物動態や安定性の評価
それぞれのステップで最先端の技術と機器が必要とされます。
以下では、各工程に対応する最新のソリューションを、実績豊富なメーカーの製品を中心にご紹介していきます。研究開発の効率化とクオリティの向上にお役立てください。
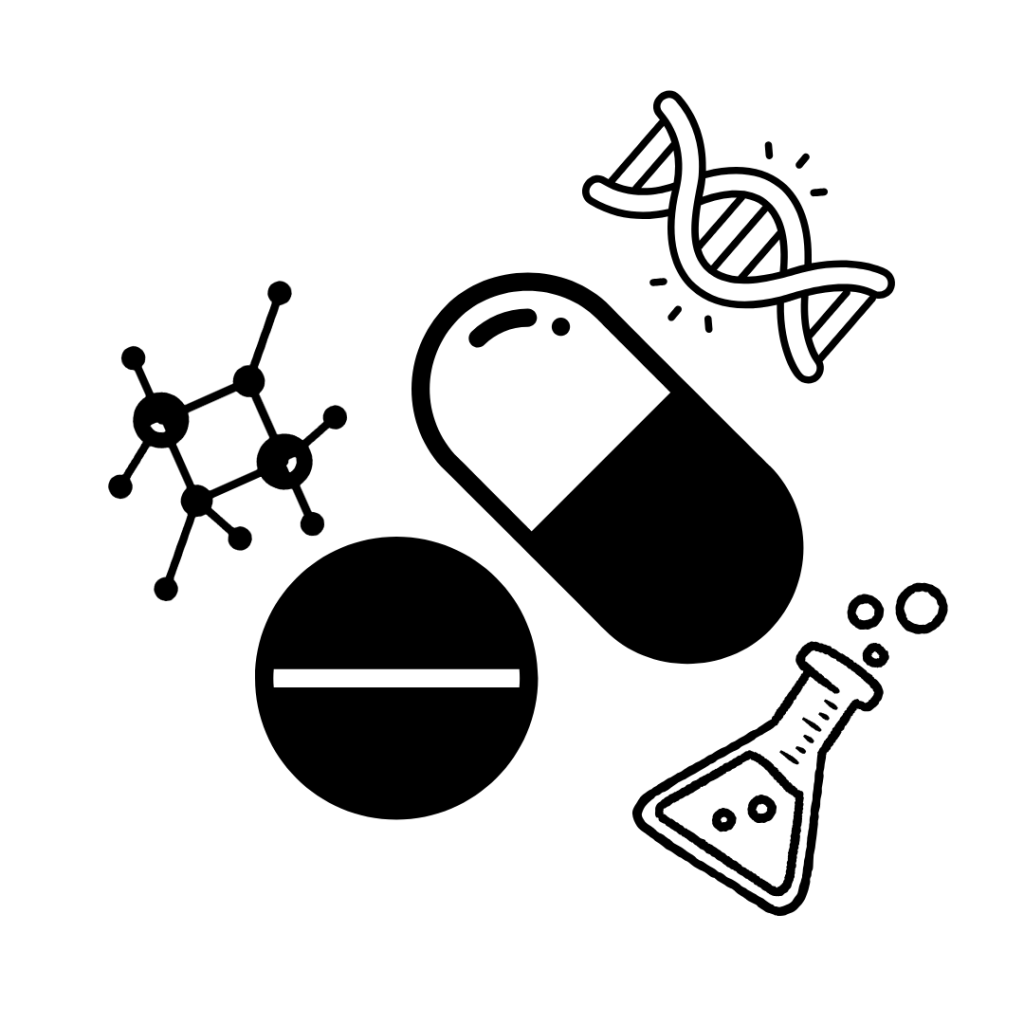
低分子医薬:分子量約500以下、従来の医薬品、化学合成で得られる化学物質
中分子医薬:分子量500~2000程度、ペプチドや核酸を使用した医薬品のことを指す
高分子医薬:分子量数千以上、抗体医薬品などバイオ医薬品ともいわれる
書籍紹介
実験医学増刊 vol.43 No.2 創薬の不可能を可能にする 中分子ペプチド医薬-低分子と抗体の利点を兼ね備えた新モダリティで活性化・機能阻害・分子間相互作用を自在に操る!
今回ご紹介する「実験医学増刊 vol.43 No.2 創薬の不可能を可能にする 中分子ペプチド医薬-低分子と抗体の利点を兼ね備えた新モダリティで活性化・機能阻害・分子間相互作用を自在に操る!」では中分子ペプチド医薬の開発の歴史や今後の展望、各種課題への取り組みなどを把握することができます。
序にかえて はじめにより
ペプチド分子が疾患治療を目的に研究されてきた歴史は長い。ペプチド領域のノーベル賞というと、日本では1984年にノーベル化学賞で受けた「ペプチド固相合成の先駆者」であるMerrifield博士のことを称えることが多いが、歴史的にみると1955年に「硫黄を含んだペプチドホルモンの合成と生化学の先駆者」であるdu Vigneaud博士がノーベル化学賞を受賞、さらに「神経ペプチドの発見」を果たしたGuillemin・Schally両博士、「神経ペプチドの放射線検出法の開発」したYalow博士(女性)が1977年にノーベル生理学・医学賞を共同受賞している。インスリンをペプチドと捉えれば、さらに遡ること1923年に「インスリンの発見」に貢献したBanting・Macleod両博士がノーベル生理学・医学賞を受賞している。日本のペプチドホルモン研究の発展に大きな貢献をした松尾壽之博士は、Schally博士のもとでノーベル賞受賞に至る研究に大きく寄与したことも忘れてはならない。また、化学分野では赤堀四郎・榊原俊平両博士のペプチド解析や合成研究も世界に先駆けた研究成果で、その後の国内外のペプチド研究の進展に大きく貢献したことは、ペプチド研究者ならば誰もが知っていることである。
引用:『実験医学増刊 vol.43 No.2 創薬の不可能を可能にする 中分子ペプチド医薬-低分子と抗体の利点を兼ね備えた新モダリティで活性化・機能阻害・分子間相互作用を自在に操る!』序にかえて はじめにより
https://www.yodosha.co.jp/yodobook/book/9784758104241/3.html
実験医学増刊 vol.43 No.2
購入申込フォーム
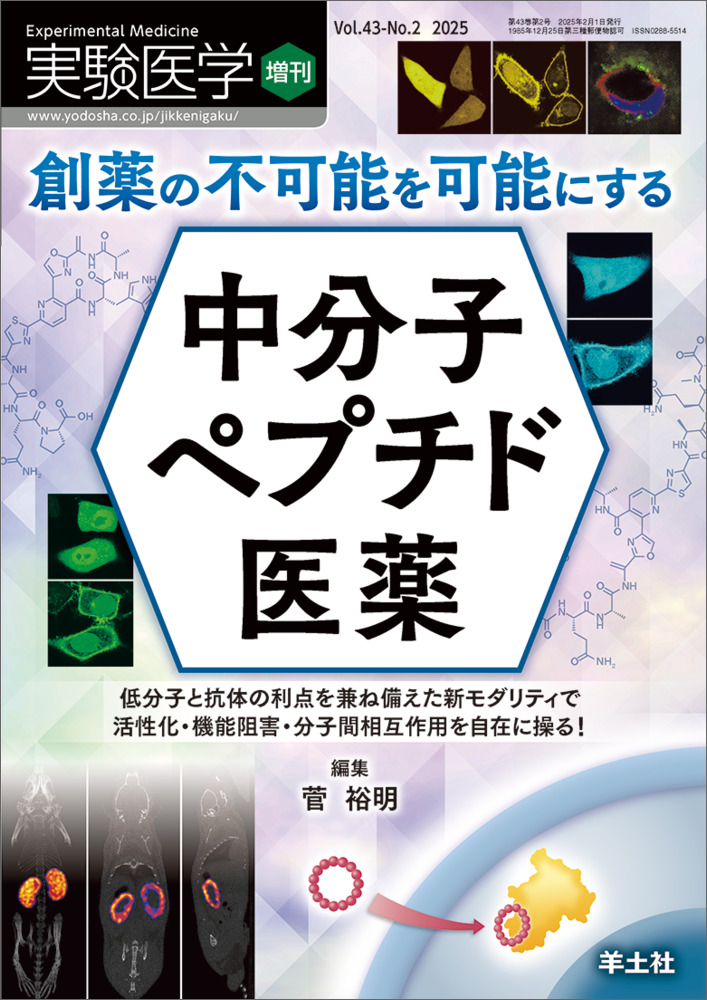
今回ご紹介の書籍をご購入希望の場合は
フォームを記入の上送信ください。
追って担当営業よりご連絡申し上げます。
ソリューション紹介
\他、創薬研究に関連する製品・サービスをピックアップしました!/